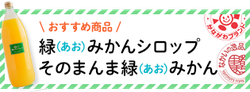近年では、夏が近づくと「異常な暑さ」「前年以上」「今年は暑い」とメディアで伝えられ、いよいよこの35度を超える日々が今の日本の夏であることを認めざるを得なくなってきています。
熱中症予防の観点から不要不急の外出を控えるように呼び掛けられていますが、外での仕事、特に第一次産業に従事している方は今日もまた、過酷な現場に出ていくのです。
ただでさえ第一次産業は後継者がいないと騒がれている中、農業という生業は、今後どのようになっていくのでしょうか。
8月下旬 曽我の山でミカンの摘果作業をしていたのは長谷川壮也(たけや)さん。
畑に入っていくと、枯れたミカンの木が伐採され、山積みになっていました。
「4年前ぐらいから、ミカンナガタマムシという今まで見なかった害虫が発生するようになってしまって、この虫の幼虫が木の中に寄生してしまうと木がものの1、2年で枯れてしまうんです。気候変動や樹齢が古いからだと半ば諦めていたんですけど、先日熊本に行った際に、今ここで問題になっているミカンナガタマムシの問題は小規模に抑えられていました。自分の畑でももっと対策ができることって思い直しました。」
かつてミカンの産地として活発であった小田原は今、新たな局面を迎えています。

農家になりたくなかった
生まれたときから農家の子で、幼少期からミカンの段ボールを組み立てたり、出荷に間に合わないと夜の8時に寝ているのを起こされて、配達に行くのを手伝ったり、家族全員で作業した思い出があります。
中学生になるとそこからは農作業らしい農作業もしなかったですね。よっぽどのことがなければ親も手伝えとは言いませんでした。
そんな自分は大学2年の頃から映像の世界にはまり、将来は映像の道に進もうと思いました。農家を継ぐことは全く考えていませんでしたね。(笑)
むしろ、「映像で食えていないなら農家を継げ!」と言われるのが嫌だったので、自分が25~30歳になるまでに、映像の道で絶対成功してやると思っていました。
ところが2008年に親父(前ジョイファーム小田原社長 長谷川功氏)が農作業中の事故で怪我を負い、集中治療室に入りました。
病院に駆け付けてすぐに意識が戻らない親父を見て、「あ、親父死ぬな」と覚悟しました。
1か月後、奇跡的に意識が回復しましたが、怪我の前はバリバリ働いていた親父が働けなくなったのを見て、なしくずしに農業の道へすすんでいくことになりました。
今は農家として働き始めて約14年です。
はじめの頃は「やらされている」と思っていましたね。農作業ってなんでこんなに時間が経たないんだ!とも思いました。好きな映像に携わっている時間は簡単に過ぎていったのに。
ただ、前職のパソコンを使う仕事から体を使う仕事に変わって、体はすこぶる健康になっていきました。そして、ちょっと間違えると怪我の危険がある仕事だと感じたときは、人に備わっている危機感がすっかり都会ぼけしてしまっていたなと思いました。(幸い大きなけがはまだしていません。)
農業を考える
人からはよく、「何を考えているか分からない」と言われる一方で、「考えすぎ」ともはたまた「お前は何も考えていない」とも言われます。(笑)
最近では農作業が好き、というよりも農業について考えることが好きなんだと分かってきました。もともと本を読んだり、時間をかけて映像を作るのが好きなので、考えることが好きなんです。
昨今は農業資材の値上げも激しく、農家が肥料についてシビアに考えなければいけないなと感じています。今まで肥料は肥料屋に買いに行って、成分も配合も、全て肥料屋に任せきりで言われるがままに使っていました。でも、自分の作物、畑の状態にあわせて配合して作れることをしたいし、それを求められる時代がやってきているのではないかと思いはじめています。
農家って独特ですよね。ただ畑をやっているだけじゃなくて、山に入って倒れた木があれば林業でもないのにチェーンソーで伐採して片付けたり、倉庫の屋根に穴が空いたら自分で修繕したり…全部自分でやっていかないとお金がかかります。
昔の農家は本当によくそういうことをしていたと思うんですよ。出来るだけ自分で身の回りのことはやっちゃう。だから百姓って言うんですよね。今は色々と用意されすぎちゃってるのかなって思います。コンビニのおにぎりって、簡単に食べられるけど割高ですよね。それだけ便利さをお金で買っているのだけど、過程が見えなくなることも多い。農業で食べることで費用をきりつめつつ品質の良いものを求めるなら、手間と知恵を惜しまないようにしないとと思うのです。
小田原の土地の特徴としては狭かったり傾斜地が多かったり点在していたり…機械化するには整備されていない土地が多すぎます。
もちろん農地を整備していくことも大事ですが、作物の収入に目標を決めて、そこからどうしたらその数字に到達するのか逆算をしなければなりません。
人海戦術で収入に見合う作物、機械を導入した方が良い作物、などを見極めて数字化しないといけないですね。
圃場の効率化はまだまだできると思っています。最近では温暖化によって作物の収量が不安定です。そうなると、計算がしにくくなるので、その暑さをどうやって乗り越えるのか。今は品種改良も進んで暑さに強い品種があるので切り替えたり、栽培時期が適切なのか見直したり、施肥設計を見直したりできます。
そんなことを考えていたら、あれだけ経たないと思っていた作業時間も、いつの間にか足らないくらいになっていました。
小田原という可能性
小田原は都心に近いものの、農業が生活に根付いていて、絶妙なバランスだと思います。後継者問題は確かに深刻ですが、過疎はすすんでいません。若者もいっぱいいます。
ただ、仕事の選択肢もたくさんあるので、農業で食えなきゃ生きていけないぞ!って危機感も薄いのかもしれません。視察で地方に行くと団結力というか、農家1人1人が本気で農業で食っていくぞって気持ちが強くて、すごいと思ったりします。そして、他産地に小田原は近郊農業で中途半端とか言われるけど、負けたくないし、既に誇れる部分もある。
最近では農産物の販路もさまざまで、昔は市場に出すのが当たり前でしたが、若い人は独自の販路も持っていて、昔のように農家同士が集まる機会も減りました。
昔の生産者は馬力もキャラも強かったと思うけど、先輩を見習いながら、今の時代に沿ったやり方だったり、アイデアを凝らして次世代の団結力を強めることができたらと思います。
ミカンへの思い
思い入れのある作物といえばミカンですね。感覚的な部分もあるのですが、うちで昔から作っていたり、いろんな作物に比べて、デリケートな作物だと思っています。手をかけてやらないと、製品にならない難しさも面白いと思っています。今のままではなかなか収益性は厳しい面もあるけど、ミカンの耕作をなくすということは考えていませんね。
もう意地になってるところもあります(笑)
今はミカンナガタマムシの被害により、全盛期の三分の一しか木が残っていません。
特に普通温州は樹勢が弱いせいか特に枯れが目立つ傾向にあります。
慣行栽培では虫の被害は少ない、と言われているが、それだけではないと思うんです。
ミカンナガタマムシは飛び回ってあちこちの畑を荒らすような虫ではなくて、畑に発生すると少しずつ次の木へと移る印象です。
全部木を枯らしたら一斉に他の畑に移るわけではなくて、隣に樹勢の弱い木があったら移るかもしれない、そのくらいかなと感じています。
実際にこの畑でも植えて10年~15年の木はほとんど枯れていない、つまり枯れてしまった木は何らかの理由で樹勢を保てていないわけです。
小田原の特徴としては、特に曽我山近辺は比較的50年ほどの老木が多いです。弱った木はあっという間に枯れますね。今日はパートさんと摘果の作業をしていますが、夏場の手入れをし損ねるというのも、樹勢が衰える理由になります。
だから今は植え替えに重点を置いて計画しています。
なんだろう、ミカンって収穫スタイルもいいですよね。1本の木を5~6人で囲んで、幅広い年齢層で、上下取る人に分担して、わいわい楽しいんです。途中にお茶の時間を畑でしたり。
手がかかるけれどなかなか価格は上がりにくく安い、そんなみかんですが、栽培をやめるつもりは今のところはありません。いつか報われることを信じて踏ん張ります。

未来を考える
うちは「長谷川農園」として人を雇って農業をしています。自分が働き始める前は人の入れ変わりが激しかったのですが今はやっとメンバーが固定してきた一方、徐々に年齢が上がってきていて、若さの馬力で乗り切れることが少なくなっています。
俺がまだまだ勉強不足だけど、計画に強くなって、最低限の出荷量は守っていきたいと思います。ベースを作ってから新規就農者の受け入れもしていきたいし、社員も増やしていきたい!
新規就農の若手に期待ばかりしているわけではなく、3~4年後どうしていくのかは既存生産者の課題でもあります。
今までの農業は農家だけが我慢する部分が多かったのですが、農家が食べていけないと日本はだめになると思います。これは農家だけが考えるんじゃなくて、地域や、消費者、行政、教育機関、関わる全ての人と、ジョイファーム小田原を通して考えていかなければいけないですね。
食べる人へ
長谷川農園って作業中に社員もパートさんたちも結構自分たちの農産物を食べています。それって生産者としては胸を張れるところで、作り手側が食べたくなる農産物なんですよね。おいしそうと思わなかったら食べないと思います。
で、実際に食べてみていろんな意見が出て、最後は皆がおいしい所までどうしたら持って行けるのか話し合うことができます。
それと、形が変なものを「ダメ」じゃなくて面白がるんですよ。顔を書いてみたり、何の形に似ているかで盛り上がったり、自然を楽しむことができます。
今、いろんな産地を視察に行って思うのは、実際に行ってみるとその土地のことを五感どころか第六感で感じることがあるんですよ。そうするとその産地の作物もまた味わい深くなる。
皆さんに小田原の農産物を食べるだけでなく、可能性があふれている小田原に交流に来てもらって、背景、歴史、ストーリーを見てもらいたいと思っています。
食べる人からの意見も加われば、さらに可能性が広がって、もっと一緒にやっていけると思うのです。